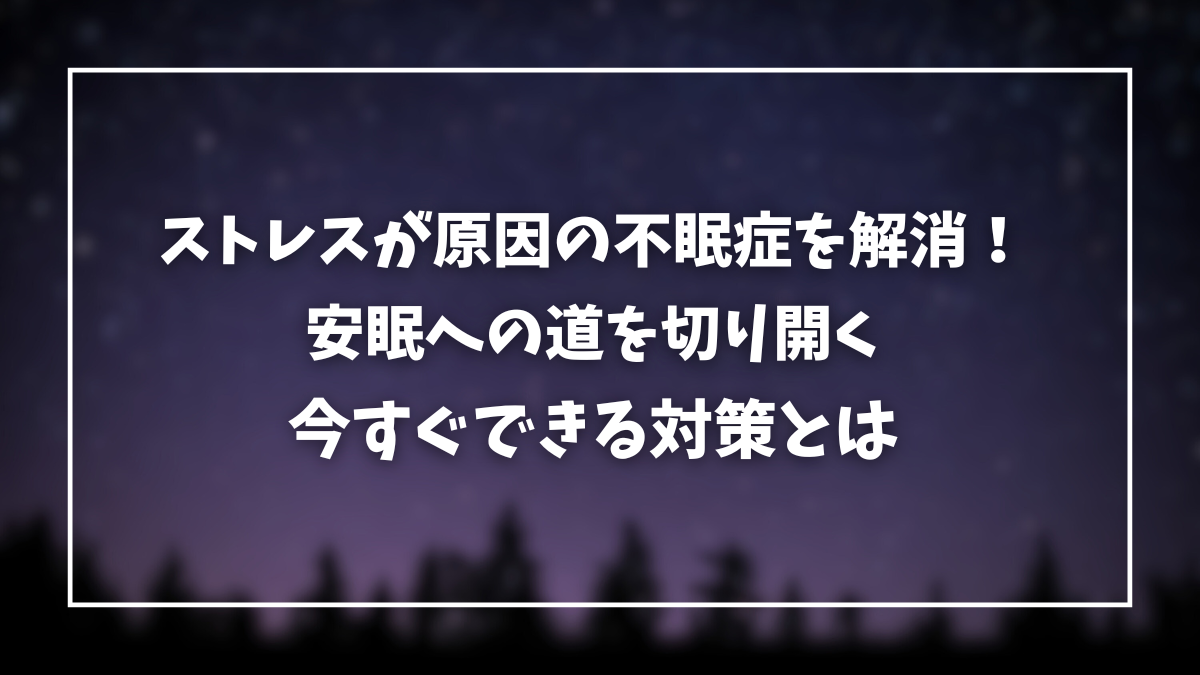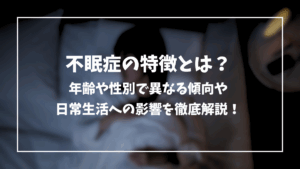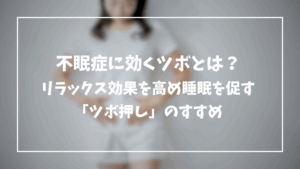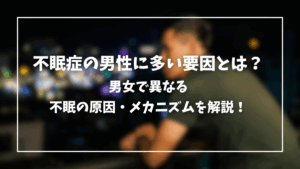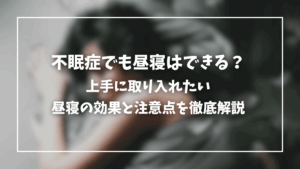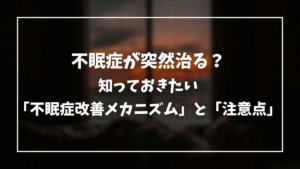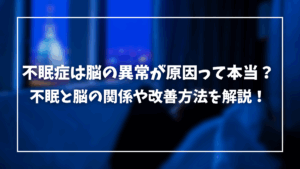実は3割以上の一般成人が症状があるといわれている不眠症。中でも主な不眠の原因とされるのがストレスです。ストレスに対する反応は人それぞれ異なり、「眠れなくなるタイプ」と「眠くなるタイプ」に分かれます。
ストレスが引き起こす不眠症の原因とその症状について詳しく解説し、今夜からすぐに実践可能な対策やセルフケアの方法を紹介します。快適な睡眠へと導く具体的な手法を徹底的にガイドします!
ストレスと不眠症の関係

現代社会では、多くの人がストレスによって睡眠の質を損ない、不眠症に悩まされています。仕事や人間関係、将来への不安など、ストレスの原因はさまざまですが、それが睡眠に及ぼす影響は想像以上に大きいものです。
ストレスは不眠を引き起こし、不眠はさらにストレスを増やすことがあります。この悪循環を断ち切るためには、ストレスを管理し、適切な睡眠習慣を確立することが大切です。
ストレスと不眠症の関係性を明らかにしながら、今すぐ取り入れられるストレス不眠の改善方法をご紹介します。
ストレスが招く不眠症の原因とは?

ストレスが不眠症の原因となることはよく知られていますが、そのメカニズムはあまり知られていません。ここでは、ストレスがどのようにして睡眠に悪影響を与えるのかを解説します。
精神的ストレスと交感神経の過剰活性化
ストレスを感じると、私たちの自律神経は「交感神経」が優位になります。これは、緊張や不安に対して体が戦闘態勢を取る「闘争・逃走反応(fight or flight)」を起こすためのものです。この状態が続くと、脳や体が常に覚醒し続け、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
さらに、交感神経が過剰に働くことで、心拍数の上昇や体温の変動など、睡眠に必要なリラックス状態が妨げられます。その結果、夜間に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまうなど、典型的な不眠症状が現れるのです。
心理的負担と寝つき・寝起きの悪化
ストレスが強くなると、就寝前に考えごとが止まらなくなる「思考過剰(racing thoughts)」の状態に陥ることがあります。これが寝つきの悪さにつながり、睡眠の質がさらに低下します。
また、睡眠中も心理的負担が夢や無意識に影響を与え、途中で目が覚めることが増えます。眠ったつもりでも脳が休まっておらず、朝起きたときに疲労感が残るケースも多いのが特徴です。
ストレスで「不眠になる人」と「眠くなる人」の違いとは?

ストレスを受けた際に「眠れなくなる人」と「やたらと眠くなる人」がいます。これは生理的反応の違いによるものであり、どちらが正常というわけではありません。その違いを詳しく見ていきましょう。
| ストレスを受けたときに | 眠れなくなる人 | やたらと眠くなる人 |
|---|---|---|
| 原因 | ストレスにより交感神経が活発になり、脳が覚醒状態になるため、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまったりする | ・ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、副交感神経が優位になることで、過眠状態になる ・ストレスによって脳が疲労し、休息を求めて眠くなる |
| 自律神経の反応 | 交感神経が過剰に働いて、覚醒状態が続く | 副交感神経が優位になりすぎて、強い倦怠感や眠気が生じる |
| 症状 | 不眠、寝つきが悪い、中途覚醒、睡眠の質が悪い | 日中の眠気、過眠、集中力低下 |
| 対処法 | ストレスの原因を特定し、解消を試みる、リラックスできる時間を設ける、睡眠環境を整えるなどが有効 | 睡眠時間を確保する、昼休憩に短い仮眠をとる、ストレスの原因を解消する、必要であれば医療機関を受診するなど |
不眠と過眠の違いは「自律神経」の反応
ストレスがかかると、交感神経と副交感神経のバランスが乱れます。不眠になる人は交感神経が過剰に働いて、覚醒状態が続きます。一方、過眠になる人は、逆に副交感神経が優位になりすぎて、強い倦怠感や眠気が生じるのです。
また、ホルモンバランスや脳内物質の分泌にも影響が出るため、セロトニンやメラトニンの生成が低下することで、眠気やだるさが強まることもあります。
ストレス反応のタイプは人それぞれ
ストレスに対する反応は個人差が大きく、「戦うか逃げるか(fight or flight)」タイプの人は交感神経が優位になりやすく、不眠傾向が強くなります。一方、「シャットダウン(freeze)」タイプの人は、体がエネルギーを温存する方向に働き、睡眠時間が長くなったり、日中に強い眠気を感じたりするのです。
このように、ストレスの影響は人によって異なるため、「自分はなぜこうなるのか」を理解することが、対策の第一歩となります。
出典:ポリヴェーガル理論|日本バイオフィードバック学会学術総会
こころとからだのセルフヒーリング(J-STAGE)
ストレス性の不眠症によくある症状とサイン

ストレスによって引き起こされる不眠症には、いくつかの典型的な症状があります。自覚しにくいケースも多いため、早期の気づきが大切です。
眠りの浅さや中途覚醒の頻度
ストレスによる不眠では、眠りが浅くなり、ちょっとした物音でも目が覚めやすくなります。また、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」が増えるのも特徴のひとつです。
これは、脳が完全にリラックスできておらず、警戒モードが続いていることを意味します。その結果、深いノンレム睡眠が不足し、心身の疲労回復が妨げられてしまいます。
日中の気分の落ち込みや集中力低下
睡眠の質が悪化すると、日中のメンタルにも影響を及ぼします。具体的には、気分が落ち込みやすくなったり、イライラしやすくなったり、集中力が続かなくなったりします。
これがさらにストレスを増幅させ、睡眠障害を悪化させる「負のスパイラル」に陥ることも少なくありません。早めに自覚し、ストレスケアや睡眠改善に取り組むことが重要です。
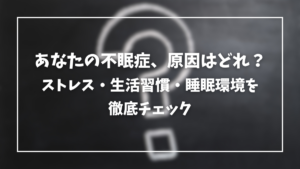
ストレスによる不眠症に効くセルフケア法

ストレスによる不眠には、セルフケアが強力な武器になります。ここでは自分でできる具体的な不眠の改善方法を紹介します。
リラックス体操やストレッチの取り入れ方
ヨガや太極拳、瞑想などは、自律神経を整え、コルチゾール(ストレスホルモン)を減少させる効果があります 。寝る前に軽いストレッチや深呼吸を1~5分行うだけでも、身体の緊張や思考の過剰活性(racing thoughts)を和らげる効果があります。穏やかな音楽やアプリのガイド瞑想を併用するのもおすすめです。
入浴やアロマなどのリラクゼーション習慣
ぬるめのお風呂(約38℃)にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、体温が下がりやすくなって睡眠誘発を促します。さらに、ラベンダーなどの香りはリラクゼーション効果が確認されており、睡眠への導入がスムーズになります。

ストレス軽減に役立つ不眠改善の生活習慣
ストレス軽減には、睡眠の質を高めることが重要です。セルフケアと同時に、日常生活に効果的な習慣を取り入れることも大切です。
就寝前のスマホ・カフェイン対策
ブルーライトや刺激的なSNSの閲覧は交感神経を活性化し、寝つきを悪くします 。就寝2時間前からスマホの画面を見るのを避け、カフェインは午後以降控えましょう。
朝の日光浴や規則的な運動習慣
日の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜間の睡眠が整います。また、日中にウォーキングや軽い運動を行うことで、夜間の深い睡眠(ノンレム睡眠)が促進され、夜間覚醒も減少します 。生活習慣でストレスを改善するには以下のようないろいろな方法があります。
- ウォーキングやジョギング、ゴルフやテニスなどのスポーツを楽しむ
- 就寝前のストレッチを習慣にする
- ガーデニングや陶芸、絵画や料理などの創作活動を楽しむ
- 旅行を楽しむ
- 家族や友人、同僚などに悩みを相談する
- 会社や近所のサークル活動に参加する
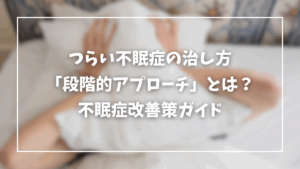
ストレス不眠時におすすめの寝具・アイテム

以下のようにグッズや音楽などを利用して効果的な睡眠環境を整えることもおすすめです。
- 耳栓やアイマスク:覚醒につながる騒音や光などを物理的に減らします。
- ホワイトノイズや癒し音:騒音をかき消すマスキング効果で気になる音の刺激を覆い隠し、リラックスを促進します。
- リラックス枕・マットレス:首・背中の負担が少ない素材を選ぶことで、身体的ストレスを軽減できます。


よくある質問
- ストレスで眠れないときすぐできる対処法は?
-
まずは深呼吸とストレッチを5分行い、スマホや時計を見るのをやめ、「寝なきゃ」と思わない練習をしましょう。どうしても眠れなければ起きて本を読むなど、軽く気を紛らわせるとよいでしょう。
- ストレスを感じやすい人に共通する傾向とは?
-
完璧主義な人、責任感が強い人、他人の評価を気にしやすい人はストレスを感じやすい傾向があります。また、環境変化への適応が苦手な人や、感受性が高い人も注意が必要です。こうした傾向がある人は、定期的なストレスマネジメントが重要です。
- ストレス性の不眠を放置するとどうなる?
-
慢性的な睡眠不足は、うつ病・不安症・高血圧・免疫力低下など健康に悪影響を与えるリスクがあります 。
- どれくらい不眠が続いたら専門医に相談すべき?
-
3ヶ月以上「週3回以上」眠れない状態が続く場合は、慢性不眠症と診断される可能性があります。セルフケアで改善しない場合は、早めに医療機関(睡眠専門外来)を受診するのがおすすめです。
- ストレスが原因の不眠はどれくらいの人が経験している?
-
厚生労働省の調査によれば、一般成人の30〜40%が何らかの不眠を経験しており、その中でもストレスが原因と考えられるケースは多数を占めています。特に仕事・家庭・人間関係などの心理的負荷は、強い影響を与えることが知られています。
まとめ
ストレスによる睡眠問題は、多くの人が抱える身近な悩みです。
ストレスによって眠れなくなる、あるいは過度に眠くなる現象は、多くの人に起こり得る一般的な反応です。特に、交感神経が優位になって脳や体が覚醒状態になると、不眠症の症状が現れやすくなります。
ストレスに対する反応は人それぞれ異なり、「眠れなくなるタイプ」と「眠くなるタイプ」がいることも理解しておくべきポイントです。自分の反応傾向を知ることで、より適切な対策を選ぶことができます。
不眠が長期化すると、うつ病や高血圧など他の健康問題につながるリスクもあるため、症状が3ヶ月以上続く場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。
まずは自分のストレスと睡眠の関係を見直し、できるところから改善を始めていきましょう。