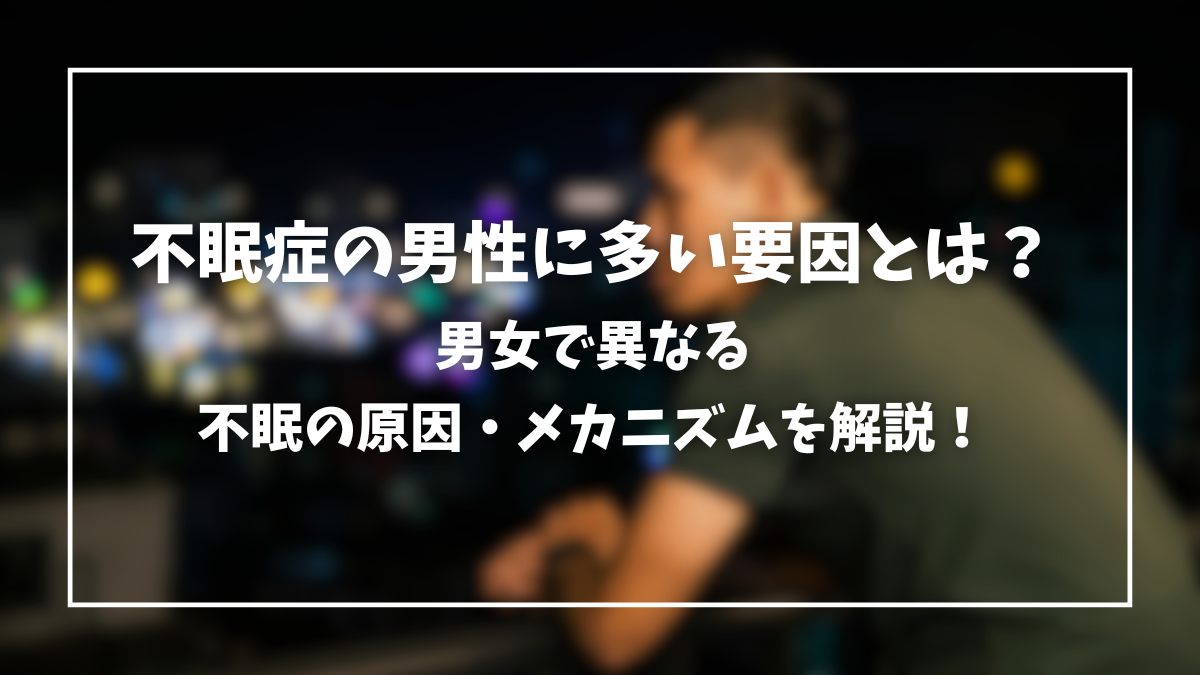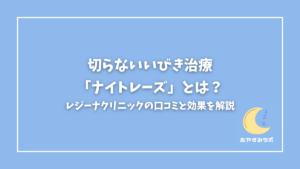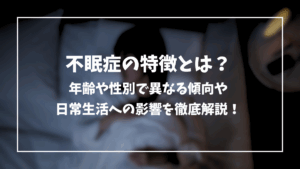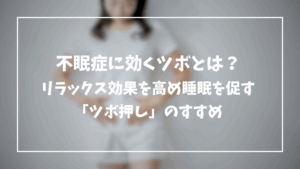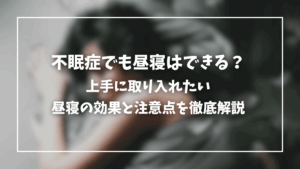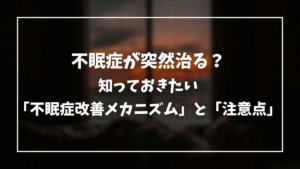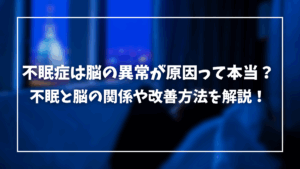不眠症は誰にでも起こり得る病気ですが、実はその原因や症状の現れ方には性別によって違いがあります。特に男性の場合、仕事や家庭の責任、生活習慣の乱れ、ホルモンの変化などが複雑に絡み合い、不眠の引き金となることが少なくありません。男性の不眠原因の視点を軸に、女性との違いや共通点も交えながら、具体的な対策を解説します。
不眠症の原因に性別差はある?

不眠症の原因には男女で違いが見られることがあります。共通する原因も多くありますが、男性の場合、ストレスや生活習慣、加齢などが不眠の大きな要因となります。性別や年齢ごとに異なる不眠症の傾向について解説します。
男性・女性の不眠症 発症率の比較
不眠症の発症率は、一般的に女性の方が男性よりも高い傾向があります。
一般成人の30~40%が何らかの不眠症状を有するとし、女性に多いことが知られている」と明記されています。また、全国健康保険協会の「睡眠実態調査報告書」では、睡眠障害による生活習慣病リスクの話に続いて、性別の差に触れていますが、背景要因には男女共通と性差が混在しています。
出典:日本の一般成人における不眠症状と性差の関連性について|厚生労働科学研究成果データベース
健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~|厚生労働省
睡眠実態調査報告書|全国健康保険協会
年齢層別での男女の不眠傾向
「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、加齢に伴い睡眠障害が増加しており、更年期に近づくと男女ともに不眠傾向が強まります。とくに男性ではアンドロゲン(男性ホルモン)の減少に伴う睡眠障害、女性では月経・妊娠・更年期におけるホルモン変動が関連しています。男女とも「睡眠の断片化」や「入眠困難」の頻度が増すのも特徴です。
ホルモンやライフイベントによる違い
男性は更年期以降にアンドロゲン低下による気分障害や睡眠の質低下がみられ、女性はエストロゲン・プロゲステロンの周期的な変化によって不眠傾向が強まります。
このように、男性の不眠には加齢にともなうホルモン変化が背景にある一方、女性の不眠はライフイベント(妊娠・産後・更年期)と連動しやすい点が異なります。
出典:健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会議事録|厚生労働省
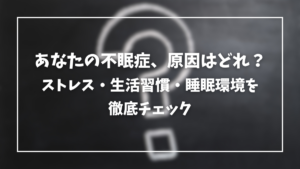
男性に多い不眠症の原因

男性に特に多いとされる不眠の要因には仕事・ライフスタイル・ホルモン変化があげられます。
仕事やストレスによる睡眠障害
20~50代の働く男性の3〜4割が「仕事が原因で眠れない」と感じており、長時間労働や職場ストレスによる交感神経の高ぶりが睡眠障害に直結することがあります。
中高年男性において、長時間労働や高負荷の仕事ストレスが交感神経を持続的に活性化させ、入眠困難や睡眠維持困難を引き起こすことがあります。
また、ストレスが持続すると睡眠ホルモンや自律神経バランスが乱れると指摘されており、日中のストレス対策が睡眠改善に効果的とされています。
出典:睡眠実態調査報告書|全国健康保険協会
健康づくりのための睡眠ガイド2023|厚生労働省
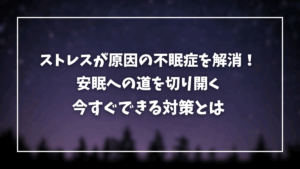
生活習慣(夜更かし・スマホ依存)と睡眠不足
成人男性の平均睡眠時間は6〜8時間ですが、現代では夜更かしや寝る前のスマホ操作が習慣化し、結果として睡眠時間が削られ、質も低下しています。
若年〜中年男性では、夜遅くまでのスマホ操作やPC作業が睡眠開始時間を後ろ倒しにし、睡眠時間の減少につながっています。
スマホやPCのブルーライトはメラトニン分泌を抑制し、入眠を妨げるため、「寝る1時間前からの使用中止」と「照明の減光」を推奨しています。
出典:良い目覚めは良い眠りから~知っているようで知らない睡眠のこと|厚生労働省
加齢・男性ホルモンの変化による影響
加齢とともに、睡眠と覚醒のメリハリが小さくなり、夜間の眠りが浅くなったり、昼間に眠気が生じやすくなったりすることがあります。
中年以降の男性ではアンドロゲンの低下が不眠や気分障害と関連し、特に更年期には睡眠障害が増加します。アンドロゲン低下はうつの誘因となり、不眠の悪循環を引き起こす可能性があります。
また、男性更年期では睡眠時無呼吸症候群や過眠の症状も報告されており、ホルモン低下だけでなく複合的な体調変化が関与します。
男女共通の不眠の原因

身体的な疾患や痛みが引き起こす不眠
性別を問わず、持病や痛みによって睡眠の質が低下することがあります。特に腰痛・関節痛・喘息・胃腸障害などは、睡眠を中断させる主因として知られています。身体的不調が原因で中途覚醒が増え、熟睡感が得られなくなるケースが多いとされています。
うつ・不安など心理的ストレスの影響
心理的要因による不眠は、男女共通でよく見られるものの、男性は「不安や抑うつ感を自覚しにくい傾向」があるため、発見や対応が遅れることがあります。男性が感情を表現する際に、社会的な制約や文化的な要因から、不安や抑うつといった感情を「弱い」と捉えがちで、言葉で表現することを避ける傾向があるためと考えられています。
夜間の考えごとや将来不安による入眠困難、早朝覚醒が特徴的です。
いびきや睡眠時無呼吸症候群とその対策
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は男性に多いとされており、中年男性の2〜3割にそのリスクがあると報告されています。SASは断続的な覚醒を引き起こし、睡眠の質が大きく低下します。睡眠中のいびき・無呼吸に気づいた場合は、耳鼻咽喉科や睡眠外来での検査・治療(例:CPAP装置)が推奨されます。
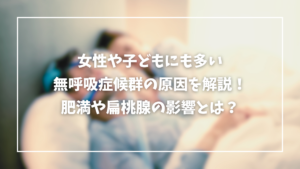
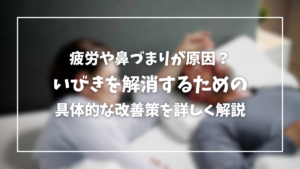
男女で異なる不眠症メカニズム

男性の不眠症のメカニズムは、女性とは異なるいくつかの要因によって特徴づけられます。特にホルモンバランスや心理・社会的背景では男女で影響を受ける度合いの差が生じています。
男性の場合、仕事のストレスや生活習慣病との相互作用や睡眠時無呼吸症候群のリスクが高い傾向があり、体内時計の周期が女性よりも長い可能性があるとされています。
ホルモンバランスの違いが 睡眠に与える影響
男性の場合、男性更年期障害(LOH症候群)では、テストステロンの減少が不眠や睡眠リズムの乱れを引き起こすことがあります。男性ホルモンは、睡眠だけでなく、筋肉量、骨密度、性機能、精神状態など、様々な身体機能に影響を与えます。
一方、女性はエストロゲン・プロゲステロンなどの周期的変化が睡眠質を左右します。
出典:睡眠の性差|日本睡眠学会
心理・社会的背景の差
女性は育児・家事負担や社会的不安によるストレスが、睡眠障害と強く結びつきやすい傾向があります。
男性は仕事のストレスや生活習慣病との相互作用で不眠が増えることが多くあります。男性は女性に比べて睡眠障害を訴える割合が低い傾向がありますが、これは男性が睡眠問題を隠したり、相談しにくい環境にあることも一因と考えられています。
男性は、仕事や経済的なことなど、抱える問題を深刻に捉える場合が多くあるため、より意識的に睡眠を管理し、必要であれば専門家のサポートを受けることが大切です。
男女別の不眠症への対策方法

不眠症への対策方法はいくつかあります。男女別の対策方法を参考に自分に合った方法で対策を講じるのがよいでしょう。
| 男性向け | 女性向け | 男女共通 |
|---|---|---|
| 生活習慣の見直しとストレス緩和 | ホルモン周期・更年期に応じたケア | 睡眠改善アプローチ |
| 生活リズムの確立 ・朝の光浴 ・夜のデジタル機器制限 ・毎日決まった時間の就寝 | ・婦人科でのホルモン補充療法 ・漢方の導入 | 就寝前の習慣の見直し ・入浴 ・読書 ・呼吸法 |
| 業務過多・責任感によるストレス対策 ・運動 ・呼吸法 ・短時間のリフレクション | 育児・家事に伴う断続的な睡眠への対応 ・パートナーや家族と役割分担 ・仮眠や昼寝で睡眠の断片化を緩和 | ・昼間の光刺激 ・活動量の確保 |
| メンタルヘルスケア 不安やうつ傾向が強い場合には、心療内科・精神科でセルフヘルプリソース(認知行動療法など)を受ける | ・心理的ストレスの緩和 ・睡眠環境 (温度・湿度・光)の整備 ・カフェインやアルコールの摂取制限 |
男性向け:生活習慣の見直しとストレス緩和
男性にとって効果的なのは、「朝の光浴」「夜のデジタル機器制限」「毎日決まった時間の就寝」などの生活リズムの確立です。また、業務過多・責任感によるストレス対策として、運動・呼吸法・短時間のリフレクションが勧められています。慢性的な不眠がある場合は、医療機関での検査も選択肢となります。
また、男性は仕事や人間関係などからくるストレスを抱えやすい傾向にあります。そこで重要となるのが「ストレスマネジメント」です。
ストレスマネジメントとは、ストレスをうまくコントロールし、健康や生活の質を維持するための方法です。具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
全てが組み合わさって、効果的なストレスマネジメントとなります。
- リラクゼーション
深呼吸や瞑想、趣味への投資等でリラックスする時間を作る。 - エクササイズ
適度な運動でストレスを発散し、睡眠の質を改善する。 - 栄養バランス
体調を整えるために、バランス良い食事を取る。 - ソーシャルサポート
人間関係の充実、話し合いや助け合いを通じてストレスを軽減する。
女性向け:ホルモン周期・更年期に応じたケア
女性はホルモン変動により、月経前症候群(PMS)、妊娠期、更年期などで不眠症状が現れやすくなります。これらに応じた対策としては、婦人科でのホルモン補充療法(HRT)や漢方の導入が推奨されることもあります。また、育児中の不眠には、家族の協力や仮眠の活用も有効です。
共通する基本的な睡眠改善アプローチ
男女問わず重要なのは、「就寝前の習慣(入浴・読書・呼吸法)」と「昼間の光刺激・活動量の確保」です。加えて、心理的ストレスの緩和、睡眠環境(温度・湿度・光)の整備、カフェインやアルコールの摂取制限なども共通の基本対策です。
男性不眠症に対する具体的な改善法

不眠の原因に合わせて、男性に特化した現実的な対策を紹介します。
生活習慣の改善(就寝ルーティンなど)
まず見直したいのが生活習慣です。毎日の就寝・起床時刻を一定に保つ「体内時計の安定」は、最も基本的かつ効果的な対策です。
厚生労働省のガイドでは、「朝の太陽光を浴び、夜は控えめな照明で過ごす」といった光のメリハリをつけた生活が推奨されています。また、夕食や入浴のタイミングを就寝2時間前までに済ませることで、体温や消化のリズムが整い、自然な眠気を誘発できます。
職場ストレスのセルフケア法
男性は仕事ストレスを抱え込みやすく、不眠症状が悪化するケースが多くみられます。
セルフケアとしては「日中のストレスを夜まで引きずらない」ことが重要です。例えば、日記に感情を書き出す「感情処理法」や、軽いストレッチ・深呼吸などのリラクゼーション法が有効です。
さらに、産業医やEAP(従業員支援プログラム)など、会社内のメンタルヘルス支援制度も積極的に利用しましょう。
専門機関・医療受診のタイミング
不眠が2週間以上継続し、日常生活に支障をきたす場合は、専門機関への受診が必要です。
特に、睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合(大きないびき、日中の強い眠気)、呼吸器内科や睡眠外来の受診が推奨されます。また、うつ傾向がある場合は、心療内科や精神科での診断と必要に応じた薬物療法が効果を発揮します。
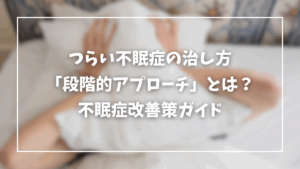
よくある質問
- 不眠症は男性に多い?女性に多い?
-
一般的には女性の方が発症率が高いとされていますが、男性も更年期以降やストレス負荷が高まったときにリスクが増します。男女で原因が異なるため、それぞれに合った対応が必要です。
- 睡眠薬やサプリは効果的?
-
一時的には効果がありますが、根本的な解決には生活改善が欠かせません。睡眠薬は依存のリスクもあるため、医師の指導のもとで使用することが大切です。
- パートナーとの睡眠リズムの違いはどう対処する?
-
生活時間帯のズレがストレスにならないよう、別々に寝る、照明・音を工夫するなどの方法があります。無理に同じペースに合わせず、快適さを重視した対話が重要です。
- ホルモン調整の治療は必要?男性の場合は何科に行くの?
-
生活習慣の乱れやストレスなどによりこれらのホルモンバランスが崩れると、体内時計が乱れて睡眠障害を引き起こす可能性があります。このような時は、ホルモンバランスを整える治療が必要となる場合もあります。男性の場合、更年期症状が強く現れるときには泌尿器科、または男性更年期外来など専門医での相談をおすすめします。
まとめ
不眠症には性別による明確な違いがあり、女性は発症率・身体的・心理的影響が男性よりやや高い傾向にあります。
男性は仕事・ストレス・生活習慣の乱れや加齢によるホルモン変化に起因することが多く、女性はホルモン周期やライフイベントに関連した不眠が目立ちます。ただし、身体的・心理的な要因、いびきや睡眠時無呼吸などは男女共通で、どちらにも起こり得る問題です。
不眠へのアプローチは性別や年齢、ライフスタイルに合った原因を正しく把握し、それに応じた対策を取ることが重要です。