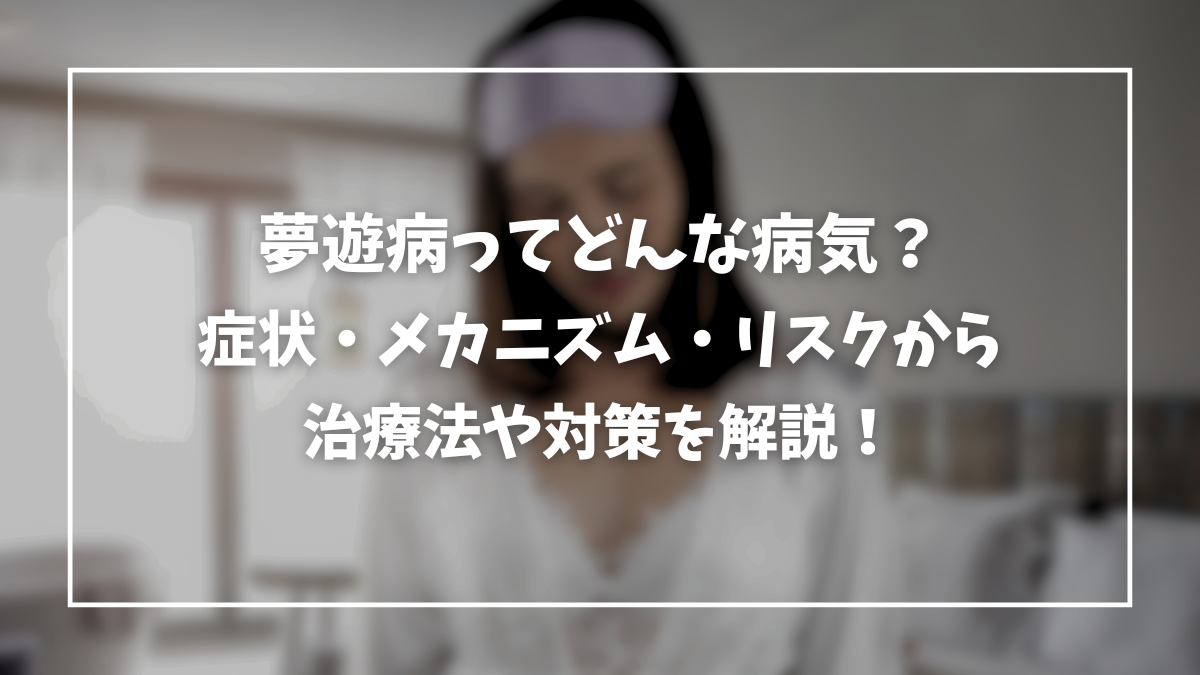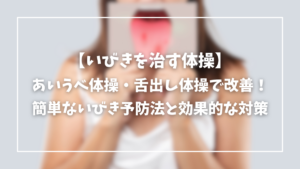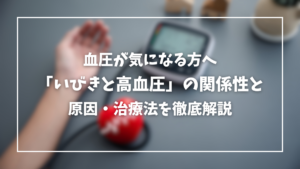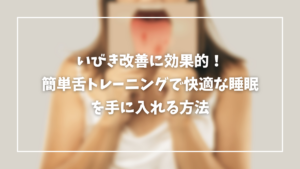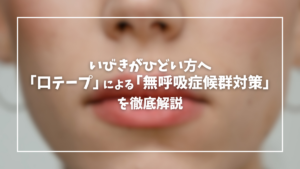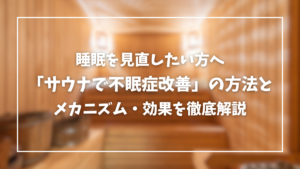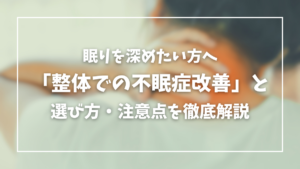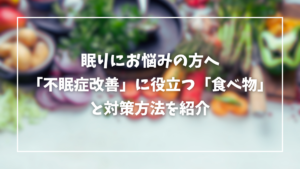夢遊病は、医学的には「睡眠時遊行症(すいみんじゆうこうしょう)」とも呼ばれ、睡眠中に無意識で歩き回ったり行動したりする睡眠障害の一種です。夢遊病は、深いノンレム睡眠中に起こり、本人に自覚がないのが特徴です。ここでは、夢遊病の症状や、発症メカニズム・主な原因・リスク要因、治療法や対策まで説明します。
夢遊病の主な特徴

夢遊病は、子供に多くみられますが、大人にも発生し、特に男性に多い傾向があります。子供は夜驚症(睡眠中に突然泣き叫んだり悲鳴をあげたりし、呼吸や心拍数が増える症状)を伴うこともあり、大人ではより危険な行動をとる場合や、他の睡眠障害を併発する場合もみられます。
| 特徴・症状 | 説明 |
|---|---|
| 発症タイミング | ノンレム睡眠中(入眠から1〜2時間以内) |
| 主な行動 | 起き上がる、歩き回る、物を動かす、外に出ようとすることも |
| 意識レベル | 呼びかけに反応しないか鈍く、翌朝覚えていないことが多い |
| 発症年齢 | 小児期に多く、成人になると自然に治まる場合もある |
夢遊病の行動の特徴とは?
夢遊病は、深いノンレム睡眠中(主に睡眠開始から1〜2時間以内)に起こる「覚醒障害」の一種です。本人は目を開けて歩いたり、座ったり、簡単な行動をとったりしますが、意識はほぼなく、会話も不明瞭です。翌朝にはその行動を覚えていないことが多いのが特徴です。
主な症状
- 寝ているはずなのに起き上がって歩く
- 呼びかけに反応が鈍い、または全く反応しない
- 無表情で、目は開いているが焦点が合っていない
- 複雑な動作(冷蔵庫を開ける、ドアを出るなど)も行うことがある
- 起こそうとしても混乱する、暴れることがある
- 翌朝、記憶がない
夢遊病のメカニズム・原因・リスク要因

夢遊病(睡眠時遊行症)は、深いノンレム睡眠から不完全に覚醒することで起こりますが、原因は完全には解明されていません。さまざまな要因があり、複雑に関与していると考えられています。メカニズムとしては、脳の一部が覚醒し、他の部分が睡眠状態のままになることが挙げられます。また、慣れない場所での睡眠や時差、基礎疾患も影響を与えることがあります。特に3歳から12歳の子供に多いのは、脳の発達が未熟なためです。
発症メカニズム(なぜ起きるのか)
夢遊病は、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)からの不完全な覚醒により起こります。
このとき、脳の一部は「覚醒状態」なのに、別の部分は「眠ったまま」というアンバランスな状態になります。その結果、本人に意識がないまま行動してしまうのです。
| 夢遊病となる きっかけ・特徴 | 説明 |
|---|---|
| ノンレム睡眠と覚醒の切り替えの乱れ | 夢遊病は、深いノンレム睡眠から完全に覚醒することなく、部分的に覚醒してしまうことで起こる |
| 脳の一部が覚醒 | 脳の一部は覚醒しているため、体が動いたり、簡単な行動をしたりすることができるが、意識ははっきりしない |
| 記憶の喪失 | 夢遊病中の行動は、本人の記憶に残らない |
| 子供に多い | 子供は睡眠と覚醒の制御が未発達なため、夢遊病になりやすい傾向がある |
| 大人にも発症 | 大人でも、ストレスや睡眠不足、アルコールなどが原因で発症する |
リスク要因(起こりやすくなる状況)
以下の要因が夢遊病の発症を引き起こす、または悪化させると考えられています。
- 就寝直後に刺激を受けたとき(電話、騒音、急な光など)
- 発熱や疲労が激しいとき
- アルコールや薬物の影響下
- 強い感情的ストレスを抱えているとき
- 睡眠時無呼吸症候群(OSA)やレストレスレッグス症候群(RLS)など他の睡眠障害の併存
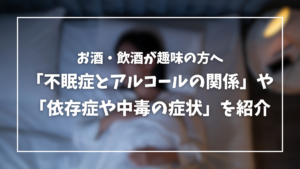
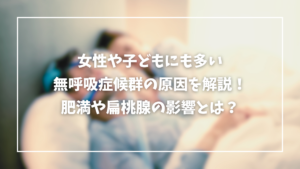
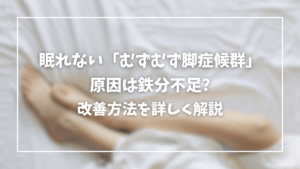
睡眠の仕組みと夢遊病の関係
私たちの睡眠は、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が交互に繰り返されるサイクルで構成されています。
ノンレム睡眠は深い眠りで、脳と体が休息し、成長ホルモンが分泌され疲労回復に重要です。レム睡眠は浅い眠りで、脳が活発に活動し、夢を見ます。
通常、深いノンレム睡眠中は脳と体が休息していますが、夢遊病では脳の一部(運動機能や覚醒に関与する領域)が部分的に“目覚めて”しまうことがあります。その結果、体は動いているものの、意識はまだ眠っているという「睡眠と覚醒の中間状態」が生じます。
夢遊病は、ノンレム睡眠の深い段階で起こり、脳の一部が覚醒している状態です。そのため、体が動いてしまうものの、意識はまだ睡眠状態にあり、行動を覚えていないことが多いのです。
夢遊病の診断・治療・対策

夢遊病の診断は、本人の自覚がないことが多いため、家族や同居者からの情報が極めて重要です。日常生活に支障をきたす場合や、事故の危険性がある場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
診断方法
夢遊病(睡眠時遊行症)の診断は、主に睡眠中の行動を観察し、問診を行うことで行われます。
具体的には、睡眠中にベッドから起き上がって歩き回る行動が見られるか、またその際に周囲にほとんど反応しないことが確認されます。
さらに、本人がそのエピソードを覚えていないことも診断において重要な要素です。
主な診断の流れ
| 診断のながれ | 説明 |
|---|---|
| 問診 | 発症状況・頻度・行動パターン・既往歴・家族歴などを確認 |
| 観察記録 | 家族による行動の記録や動画が役立つことも |
| 睡眠検査(PSG) | 睡眠ポリグラフ検査により睡眠中の脳波・筋電・呼吸・眼球運動を記録し、他の睡眠障害との区別を図る |
| 除外診断 | てんかん、睡眠時無呼吸症候群など類似疾患との区別が必要 |
治療法
夢遊病の多くは子どもの場合、成長とともに自然に改善します。成人では原因への対処が重要です。夢遊病の治療法は、環境調整、生活改善、ストレス管理、薬物療法などがあります。多くの場合、成長とともに自然に改善しますが、症状が強い場合は専門医による治療が必要になります。
治療のアプローチ
| アプローチ | 具体例 |
|---|---|
| 環境調整 | 寝室の危険物を除去、ドア・窓のロック、安全対策の徹底 |
| 生活改善 | 規則正しい生活、十分な睡眠時間の確保、昼寝の調整など |
| ストレス管理 | リラクゼーション、カウンセリング、認知行動療法(CBT)など |
| 薬物療法 | 必要に応じて、ベンゾジアゼピン系薬(例:クロナゼパム)や抗うつ薬を使用することも。ただし慎重な管理が必要 |
再発予防・家庭でできる対策
夢遊病(睡眠時遊行症)の再発予防と家庭でできる対策は、安全の確保、睡眠環境の整備が中心となります。
安全確保の工夫
- 就寝前に部屋を片付けておく
- 階段やベランダへのアクセスを制限
- 家族や同居者が異常行動に気づけるようにしておく(ベビーセンサーなども有効)
睡眠環境の整備
- 寝る前にリラックスする習慣(読書、入浴、軽いストレッチ)
- 就寝・起床時刻を固定
- カフェインやアルコールの摂取を控える
よくある質問(FAQ)
- 夢遊病の最中に起きている人を無理に起こしても大丈夫?
-
基本的には無理に起こさない方が安全です。
夢遊病中の人は意識が朦朧としており、急に起こすと混乱したり、暴れたり、パニックになることがあります。安全を確保した上で、静かに声をかけながらベッドへ誘導しましょう。 - 本人は夢遊病の行動を覚えている?
-
通常は記憶に残っていません。
夢遊病は「深い眠り」の状態で起こるため、脳が記憶を形成する機能が働いていません。そのため翌朝本人に聞いても、「覚えていない」「夢だと思った」と答えるケースがほとんどです。 - 夢遊病は治るものですか?
-
多くは自然に治りますが、大人の発症は要注意です。
子どもの場合は成長とともに改善することが多いです。一方、大人になっても続く、または突然発症した場合は、何らかの病気やストレスのサインである可能性があるため、早めの受診が勧められます。 - 夢遊病と夜驚症は違うの?
-
異なる睡眠障害ですが、どちらもノンレム睡眠中に起こります。
症状 夢遊病 夜驚症 主な行動 歩き回る、座る、無目的な行動 突然叫ぶ、泣き出す、恐怖で目覚める 意識 ぼんやりしていて反応が鈍い パニック状態で取り乱す 記憶 ほとんどなし まったく覚えていないことが多い - 睡眠薬を使えば夢遊病は治りますか?
-
原因によっては薬が使われることもありますが、基本は生活習慣の見直しが中心です。
医師の判断で抗不安薬や睡眠導入薬が処方されることもありますが、自己判断で薬を使用するのは危険です。 副作用でかえって夢遊症状が悪化するケースもあります。 - 家族はどう対応すればいい?
-
驚かず、冷静に対応することが大切です。注意するポイントは以下のとおりです。
- 危険な行動をしていないか静かに見守る
- 怪我のリスクがある場合は環境を整える(家具の角を保護する、鍵をかけるなど)
- 規則正しい生活リズムを支える
- 本人を責めたり、恥ずかしがらせたりしない
まとめ
夢遊病は、脳が部分的に覚醒してしまう睡眠の不均衡状態によって起きます。深いノンレム睡眠中に不完全な覚醒が起こることで、本人に意識がないまま行動に移ってしまうのです。発症には遺伝、環境、ストレス、睡眠不足など複数の要因が関係しています。
夢遊病の診断には専門的な問診と睡眠検査が必要であり、治療は主に生活習慣の見直しと環境整備、必要に応じた薬物療法です。本人の安全を第一に考え、家族や周囲の協力が不可欠です。特に子どもの場合、過度な心配は不要ですが、定期的な経過観察が重要です。
まずは専門家への相談を検討し、適切な治療と生活習慣の見直しをすることで、睡眠障害と夢遊病の改善を目指しましょう。